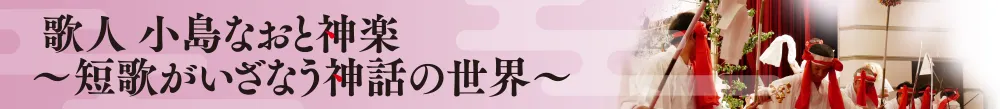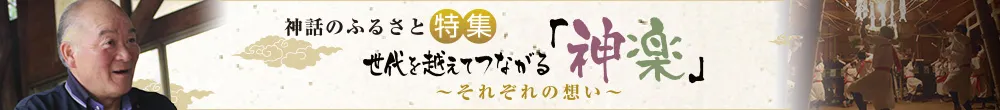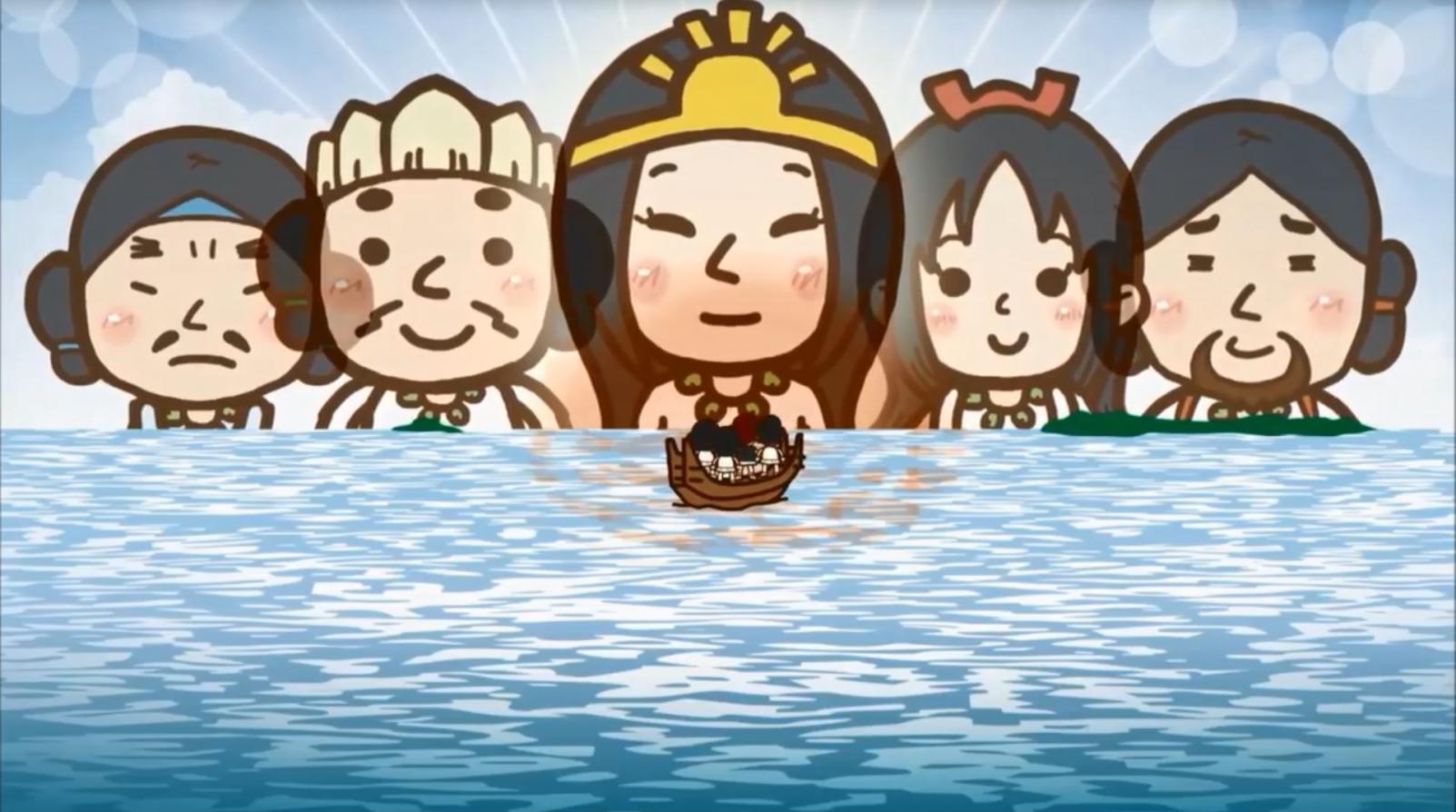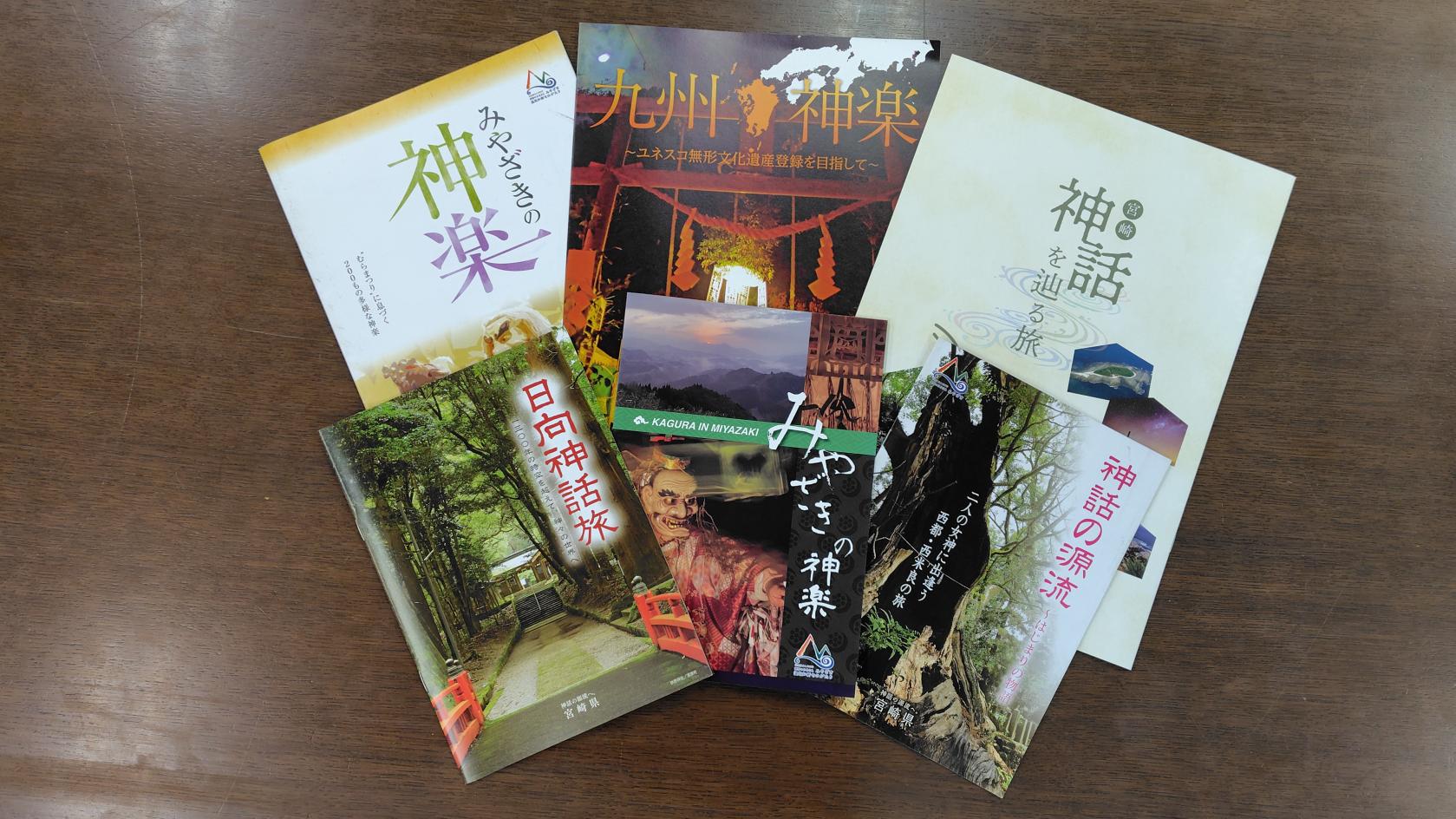宮崎の神楽
11月半ばになると、山里の集落に笛の音、太鼓の鼓動が響き渡ります。
今年もまた、天と地から恵みを授かったことに感謝を捧げ、多くの神々と舞い遊ぶ一夜が始まります。
宮崎県内各地に今も伝わる伝統の神事「神楽」。
高千穂の夜神楽を中心に、ちょっとのぞいてみましょう。
見どころは?
神楽当日まで、神楽宿のしつらえの準備が行われています。神楽を舞う神庭(こうにわ)のしめ縄や彫り物(えりもの・周囲にめぐらせる切り紙)などの美しいしつらえ、集落に数百年も伝わる貴重な御神面など、見どころもたくさん。
神楽は、午後2時ごろからの神迎えという神事から始まります。道行(みちゆき・神楽宿に土地の神々をお連れするための御神幸)から、神楽宿への舞い入れとなります。午後7時ごろから翌朝まで、33番を舞い明かします。
地元の人たちと一緒に、歩きながら神楽宿に向かうと、太鼓や笛の音が近づいてきます。子どもたちは駆け出して行って、その音に合わせて自然と体を動かします。幼いころから体に染み付いている神楽のリズム。名人の舞いの見どころは、特に脚さばきにあるそうです。太鼓や笛などのお囃子も、交代をしながら集落のほしゃどん(奉仕者)が奏でます。
地域によってはほしゃどんだけでなく、一般の飛び入り可能な番付があります。男性や子どもがほとんどですが、衣装や面を付け、神楽を存分に味わうことができます。子ども神楽や夜中の番付など、質問したいことがあったら、屋外で火を囲んで暖をとりながら、話しかけてみてください。
夜が白々と明け始め、天岩戸を開く「戸取」の後、「日の前」の舞とともに朝日が神庭に差し込んでくると、座は感動に包まれます。最後は見物客も一緒に参加し、神庭の上にある「雲」と呼ばれる天蓋から紙吹雪が舞い散り、フィナーレを迎えます。
里人たちの思い
集落に長く長く受け継がれてきた神楽。公民館や神社境内などが神楽宿となることも多いですが、自宅が神楽宿となる集落も残っています。その場合は神庭を構えるために設計されており、「神楽を舞える家を建てるのを目標にしている」という言葉が聞かれるほどです。かつては、一家の長男のみが舞うことを許され、直会の食事作りを含め、一切を男性が取り仕切っていました。神楽で舞うことは憧れだったそうです。変化してきた部分もありますが、祖先から受け継がれてきた神楽への思いを感じてみてください。
県内各地の主な神楽
各地を回ると、しつらえや番付、衣装などもそれぞれで違います。各地域で異なる神楽の魅力を発見してください。夜神楽だけでなく、昼神楽もあります。
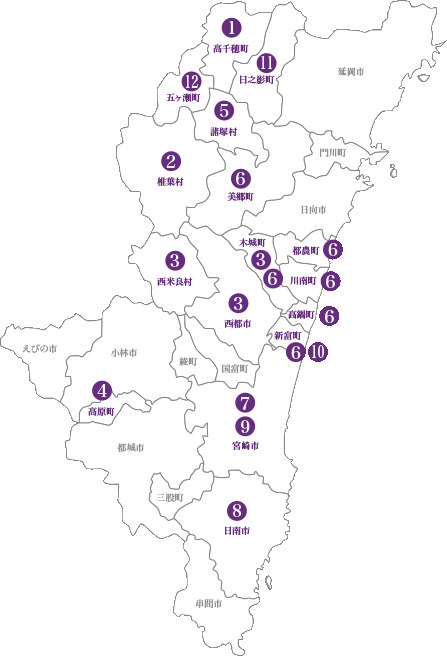
-
①高千穂の夜神楽
もっと見る高千穂町 町内30カ所ほどで伝承
国指定重要無形民俗文化財[毎年11月から翌年2月]
▶秋元神楽体験レポート
▶下野神楽体験レポート -
②椎葉神楽
もっと見る椎葉村 村内26カ所ほどで伝承
国指定重要無形民俗文化財[毎年11月から12月]
▶尾前神楽体験レポート
▶大河内神楽体験レポート -
③米良の神楽
もっと見る「銀鏡神楽」「尾八重神楽」「中之又神楽」「越野尾神楽」「村所神楽」「小川神楽」
国指定重要無形民俗文化財〔毎年11月から12月〕
▶銀鏡神楽体験レポート
▶村所神楽体験レポート
▶小川神楽体験レポート -
④高原の神舞
もっと見る国指定重要無形民俗文化財
「狭野神楽」[毎年12月第1土曜]「祓川神楽」[毎年12月第2土曜]
▶狭野神楽体験レポート
▶祓川神楽体験レポート -
⑤諸塚神楽
もっと見る諸塚村 村内3カ所
県指定無形民俗文化財
[戸下夜神楽:1月の最終土曜日/南川夜神楽:2月の第1土曜日/桂神楽:不定期]
▶南川神楽体験レポート
▶戸下神楽体験レポート -
⑥高鍋神楽
もっと見る「比木神楽」「都農神楽」「三納代神楽」「神門神楽」
県指定無形民俗文化財[毎年12月から1月]
【六社連合大神事】
[白髭神社(川南)]
[平田神社(川南)]
[八坂神社(高鍋)]
[愛宕神社(高鍋)]
[八幡神社(新富)]
[比木神社(木城)]
の旧郷社六社を年巡 -
⑦船引神楽
もっと見る宮崎市清武町
県指定無形民俗文化財
[毎年3月21日(春神楽。奉納は日中)稲作に関する「作神楽」を日中に奉納。]
▶船引神楽体験レポート
-
⑧潮嶽神楽
もっと見る日南市北郷町
[毎年2月11日(建国記念日)]
▶潮嶽神楽体験レポート
-
⑨生目神楽
もっと見る宮崎市生目
県指定無形民俗文化財[3月15日に近い土曜日] -
⑩新田神楽
もっと見る新富町新田
県指定無形民俗文化財[2月17日]
▶新田神楽体験レポート -
⑪日之影神楽
もっと見る日之影町 町内27ヶ所
県指定無形民俗文化財[毎年12月から翌年2月]
▶大人神楽体験レポート -
⑫五ヶ瀬の神楽
もっと見る五ヶ瀬町 町内5ヶ所
五ヶ瀬町無形民俗文化財[毎年11月から翌年1月]
神楽鑑賞のマナー
神楽は、地域の人が神々と一体となる儀式です。そこに参加させていただくという気持ちで訪ねましょう。
神楽を舞う神庭の中は、一般客、特に女性は立ち入り禁止という場合がほとんどです。
しきたりに従い、分からないことは尋ねましょう。
ビデオやカメラで撮影する場合は、三脚を禁止しているところも多いため注意してください。
参考:「祈りと伝承の里 高千穂の夜神楽」
-
①スケジュールを確かめます
代表的な高千穂神楽の場合、午後2時ごろからの神迎えや道行などから見ることができます。一晩中、神楽宿で鑑賞することは可能ですが、近くで宿が取れる場合は、時々、宿で休憩を取りながら鑑賞することをおすすめします。地元の人と同じように、歩いて神楽宿に向かうのもいい体験です。フィナーレ、神様をお送りする神送りまで翌朝まで執り行われます。
-
②防寒具、懐中電灯の準備を
神社の境内や、民家で行われることが多く、窓を開け放した状態なので、防寒具は必須。カイロや毛布を持参しましょう。宿泊所や車を停めた場所から夜道を歩くので、懐中電灯も持っていると安心です。雪が降り始めた場合に備えて、車のチェーンも準備しておきましょう。
-
③お供えを準備
鑑賞する場合は、焼酎2本(地元の酒屋で頼めば、地元の焼酎に熨斗を付けてくれます)か、それに相当するお金(2千~3千円程度。ご祝儀袋に御初穂または御神前と書きます)をお供えするのがマナーです。神楽宿に到着するまでに、焼酎やご祝儀袋、細かいお札、筆記用具などを準備しておきましょう。
-
④食事や飲み物も
地域によっては、竹筒で焼酎を温めた「かっぽ酒」や煮しめなどが振る舞われる場合もありますが、儀式料理のため供されない地域もあります。食事や、温かい飲み物は自分で準備しておきましょう。