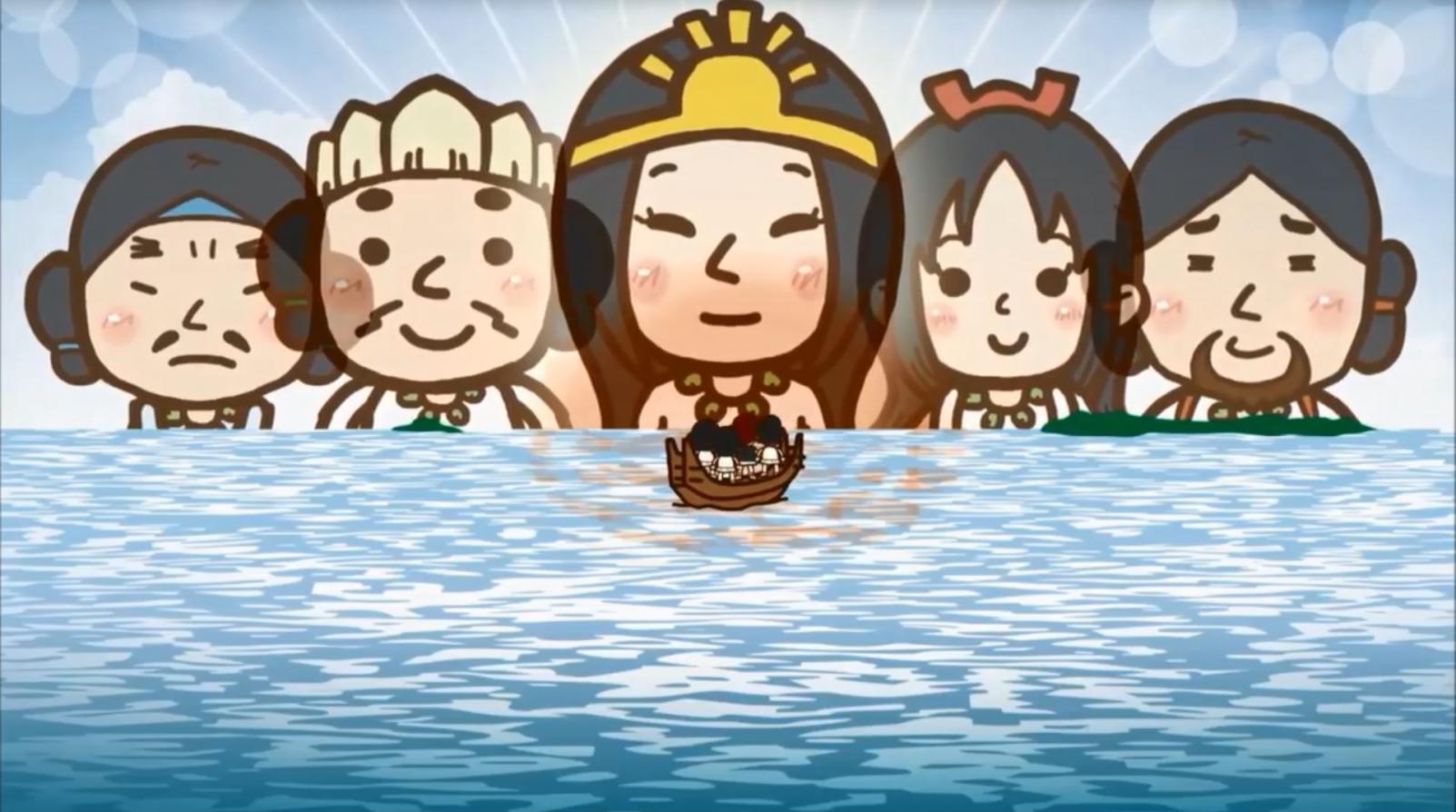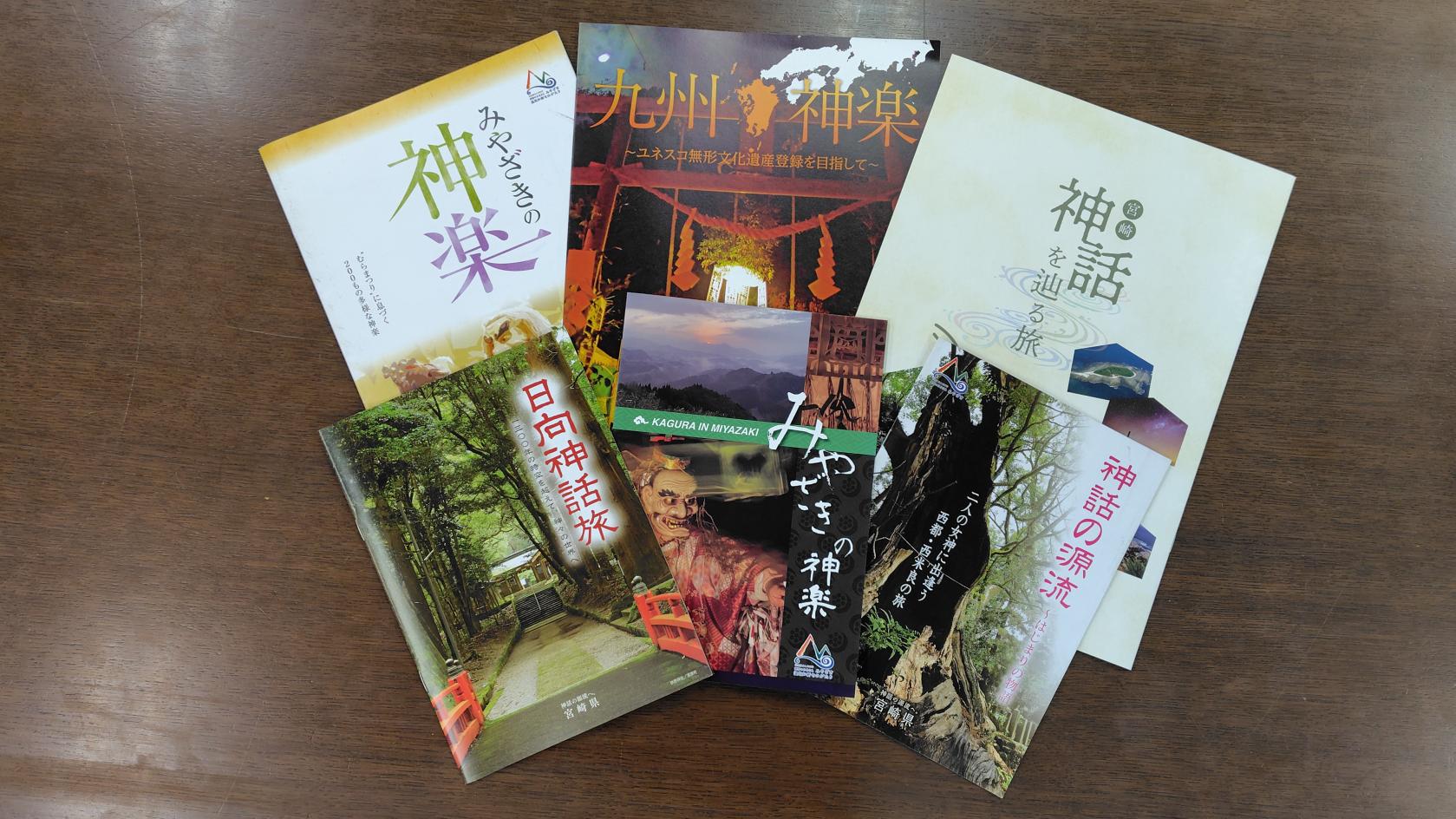神話のふるさと宮崎 神楽体験レポート~狭野神楽~
地域で大切に継承されている、勇壮な神楽
2017年12月2日鑑賞
天孫降臨の地と伝わる高千穂峰の麓に位置する高原町は、神武天皇ゆかりの地が数多く残り、また「高原」の名はかつて神々が暮らした「高天原」に由来するといわれるなど、神話が息づくまちです。そんな高原町にある狭野神社に伝わる狭野神楽は、500年以上の歴史を持つとされ、剣などを用いた勇壮な舞が多いことが特徴です。同じ高原町の祓川神楽とともに、「高原の神舞(かんめ)」として国の重要無形民俗文化財に指定されています。
<保存会名>狭野神楽保存会
<開催場所>狭野神社第2鳥居
< 実施日 > 12月第1土曜日
シチュエーション
狭野神楽は毎年12月の第1土曜日から翌日にかけて奉納されます。夜の帳が降りる頃、大勢の人が神楽を見に集まってきます。
舞
狭野神楽は、狭野神社の氏子によって継承されてきましたが、担い手となる舞手が少なくなってきたことにより、20年ほど前から地域の行事として行われています。子ども達に舞を教えたり世話をする大人の姿、神楽を見に訪れる町内外の人々、そういった光景は、まさに神楽が地域コミュニティの維持・活性化に資する役割をも果たしていることを教えてくれます。
-

踏剱(ふみつるぎ)。大人2人の持つ剣の先端を男の子が素手で握り、でんぐり返りなどの動作を行います。見所が多く、思わず目を奪われてしまう注目の演目です。
-

箕舞(きねめ)。杵などを使った舞に続いて、箕を持ち肩に乗った舞手が紙を撒きます。籾殻を飛ばす動作を表しているそうで、五穀豊穣に対するお礼の舞だそうです。
-

花舞(はなまい)。狭野神楽の将来を担っていくであろう子ども達の舞です。大人に負けじと息を合わせて舞う姿を応援せずにはいられません。
-

本剱(ほんつるぎ)。夜も更けた頃、観客が少なくなってしまう時間帯ですが、真剣を2本用いた勇壮な舞が舞われています。
-

御酔舞(ごすいまい)。おそらく狭野神楽でしかお目にかかれない舞で、なんとお酒(焼酎)を飲みながら舞います。酔っ払ってしまわないか、気になってしまいます。
神楽グルメ
舞庭の外では、神楽を見に来た方々に対して、神楽そばが振る舞われていました。寒い中いただく温かいおそばの味はまた格別でした。